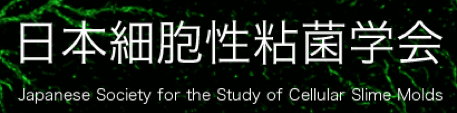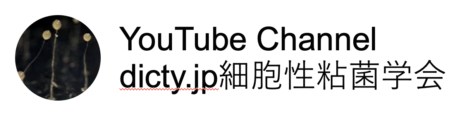お知らせ:Information
- 2024-04-01
- 2024年度春学期のスタートです。
Team Dictyに新メンバー3名(B4: 3名)が加わりました。 - 2024-03-25
- 2023年度学位授与式がありました。
当研究室からは、大学院前期課程5名が修了、学部生5名が卒業しました。おめでとうございます。
- 2023-11-01
- S, Nezuさん(生合成班:M2)、R. Suzukiさん(生合成班:M1)とS. Fuchimotoさん(化学生態学班:M1)が、第96回日本生化学会大会(福岡国際会議場・マリンメッセ福岡B館)で研究発表を行いました。
- 2023-10-21
- K. Hayashiさん(化学生態学班:M2)が、日本細胞性粘菌学会2023年度例会(九州工業大学)で研究発表を行いました。
- 2023-09-21
- 2023年度秋学期のスタートです。
Team Dictyに新メンバー1名(Green Science Course B4: 1名)が加わりました。
研究内容:Research
細胞性粘菌とは...
細胞性粘菌(学名 Dictyostelium discoideum:和名 キイロタマホコリカビ)は土壌中に生息する原生生物で、その生活史の中に単細胞の時期と多細胞の時期を持っています。単細胞の時期には細菌などを餌として盛んに分裂を繰り返しますが、餌がなくなると細胞集合を開始して、多細胞体を形成します。この多細胞体はおおよそ24時間の形態形成の過程を経て、柄細胞と胞子細胞のわずか2種類の細胞からなる子実体を形成します。子実体を形成する過程には細胞運動、細胞分化、パターン形成などの過程を含んでいます。またゲノム解析の結果、数多くの二次代謝産物を合成する酵素遺伝子があることがわかりました。特にポリケタイド合成酵素(PKS)では、I型PKSとIII型PKSが融合したハイブリッド型PKSである “Steely”酵素を持つことがわかりました。
化学生態学「生物が発する「言葉」を知る」
細胞性粘菌は土壌に住む微生物です。土壌微生物は、いろいろな化学物質を作り出して互いにコミュニケーションを取っています。このような化学物質は細胞が発する「言葉」と考えられます。その細胞の言葉の一例が抗生物質です。細胞性粘菌は農業分野で問題になっている土壌病害を引き起こす植物寄生性線虫を寄せ付けない化学物質を作っていることがわかりました。新しい土壌病害防除法の開発につなげたいと思います。
生合成研究「微生物を使った化学物質の合成」
生物が化学物質を作り出す過程を「生合成」と呼びます。通常は複数の酵素が協力して一つの化学物質を作り出します。生物によるものづくりは副産物が少なく、効率的でさらに環境負荷が少ないのが特徴です。そこでこのしくみを理解して、酵素の遺伝子を改変して新しい化合物を作り出したいと考えています。
参考書籍
- 別府輝彦「見えない巨人―微生物」ベレ出版 2015年
- ポール G. フォーコウスキー「微生物が地球をつくった -生命40億年史の主人公-」青土社 2015年
- Richard H. Kessin “DICTYOSTELIUM” Cambridge University Press 2001